10歳までに
身につけたい。
読解力・思考力・表現力が育つ
能力開発教室
将来、難関校への進学を考えているけど、小学低学年の今から何か準備をしておきたい。でも、がつがつ勉強はさせたくない。そんなお子さまのための能力開発教室です。いわゆる「お勉強」ではなく「習いごと感覚」で通え、「自分で考える力」「学びとる力」が身につき、近い将来「あと伸び」する能力を育てることができます。
あすなろ学習会とは
-
「あすなろ学習会」は、難関公立高校受験塾「駿台・浜学園」の小2生・小3生の独自学習プログラムです。

2020年度の入試改革を境に、これまでにないレベルの変革期を迎えることになります。従来の1点刻みの試験形式ではなく、「思考力」「判断力」「表現力」を問う形式に切り替わります。
あすなろ学習会は、単なる反復やパターン化された読解問題では身につかない「創造力」と「表現力」を手に入れてもらうためのプログラムを実施しています。

身につく4つの力
-
チカラ
1暗記に頼らず“自分で考える力”で
答えにたどりつける暗記やパターン学習に頼った勉強は、テストで得点を取る技術としては有効です。しかし、初見の問題や答えのない問題、さらに自ら課題を見つけ探求していく場面では、どうでしょうか?知識やパターンだけで対応できない問題に直面したとき、本当に役に立つのは「考える力」です。
考える力があれば、自分で工夫して答えを導くことができます。糸口となる情報を見つけじっくり考える。この習慣と力を低学年のうちに蓄えておくと、いわゆる「あと伸び」につながっていきます。
じっくり見る、じっくり読む、じっくりイメージする、じっくり言葉にする・・・。あすなろ学習会では、暗記やパターンに頼らず一つひとつのプロセスを味わう体験をすることで、考える力、基礎能力を確かなものにしていきます。

難関校をみすえるなら、自分で考える力が必要 -
チカラ
2知力の土台となる
イメージング力が育つ頭の中で物事や形をイメージしそれらをアウトプットする力は、知力の土台です。小学高学年でつまずきやすい文章題・国語の読解など、どれも「文章や文字から正しくイメージできるか?」「正確にアウトプットできるか?」が重要になります。考えることとはイメージできること、そして絵や図、言葉にできること。
あすなろ学習会では、国語で1冊の本を1ヶ月かけじっくり読むこと(スローリーディング)を通して情景や登場人物の関係性などを想像する方法でイメージング力を高めていきます。

しっかりした基礎は中学生での伸びにつながる -
チカラ
3「考える=楽しい」という感覚から、
学びとる力が身につく暗記やパターン学習は、正解へ早くたどり着くための手段です。小学低学年でショートカットに慣れてしまうと、じっくりプロセスを経た思考に抵抗を感じるようになります。難しい問題を目の前に「考えるのがめんどう・・・」と感じ、ますます考える楽しさや習慣が定着しません。
あすなろ学習会の生徒は、自分で考えて考え抜いてやがて発見することで、楽しい!を実感します。考えることそのものを楽しいと感じ、自ら学びとる力が日常的に備わります。それを育むために、安易に正解を教えるのではなく、生徒が考える余白を用意し「気づかせる」指導を行っています。

習いごと感覚で通え
楽しみながら学びとる力がつく -
チカラ
4あらゆる教科で発揮する
「やり抜く力(GRIT)」あすなろ学習会では、ことばを通じて「やり抜く力(GRIT)」を伸ばす取り組みをしています。近年、やり抜く力(GRIT)は、才能や環境に影響されず、なにかを成し遂げる力として注目されています。
ことばは人により捉え方が変わる多面的な要素を持っているため、必ずしも答えが1つではありません。その分、「分からない状態」「感じたことを言葉にできないもどかしさ」「多様な人の意見に耳を傾けるむずかしさ」などが生まれ、継続的で粘り強い姿勢が必要になってきます。
それがやり抜く力につながり、国語に限らずあらゆる教科で発揮されるようになります。小学低学年からGRITを養うことで、中学生、高校、さらには社会人になっても、強い味方になってくれます。

あらゆることで
やり抜く力が武器になる
読解・思考・表現力教室NATIONAL LANGUAGE
国語はすべての教科の土台
日本語で読み(読解)、考え(思考)、表現する力は、すべての教科の土台になります。
特に小学低学年の国語は、絵本から文章に変わる大事な時期。そのゴールデンタイムに、物事を深く考える経験や多面的な視点でとらえる習慣、自分の考えをシェアする機会を増やすことで、すべての教科によい影響を与えます。その基礎力が、高学年、中学高校、大学、さらに社会人においても大きく活きていきます。
1冊の本を1ヶ月かけてじっくり読む

- スローリーディング(味読)
- 灘中学・高校の元名物教師、橋本武先生が始めた読書法
1冊を1ヶ月かけてじっくりと読みます。調べる、考える、イメージする体験を経ることで、読書の楽しさを知り、味読を通して想像力や教養力、論理的思考力が身につきます。
さまざまなジャンルに出会う多読
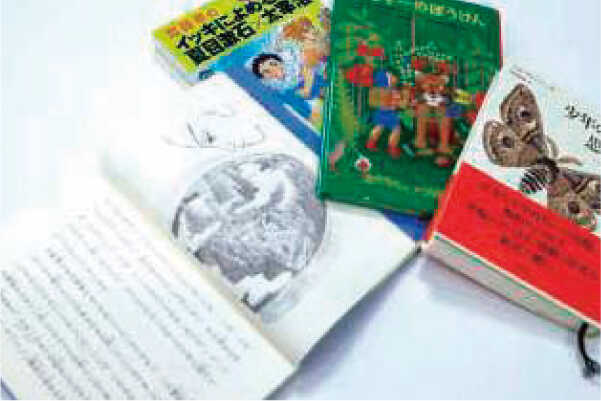
年間50冊を目標に、好きなジャンルからさまざまな本に出会います。読んだ作品を先生や友達と共有することで、多様な視点で物ごとを見る力、言葉にする力、表現力などが磨かれます。
論理的に表現する力

文章を漫然と読むのではなく、要点に焦点をあわせて読む練習をします。その上で、論拠を持って発表する、書き表すトレーニングをすることで、入試でも役立つ表現力の基礎が身につきます。
コース紹介読解・思考・表現力教室

対象学年 将来、難関公立高校をめざす小2・小3生
教科 国語(読解・思考・表現力教室)
授業料 週1回(60分):4,950円(税込)
| 小2 | 小3 | ||
|---|---|---|---|
| 校舎 | 国語 | 国語 | |
| 千里中央教室 | ◯ | ◯ | |
| 緑丘教室 | ◯ | ◯ | |
| 阪急豊中教室 | ◯ | ◯ | |
| 緑地公園教室 | ◯ | ◯ | |
| 茨木教室 | ◯ | ◯ | |
| 五月が丘教室 | ◯ | ◯ | |
| 高槻教室 | ◯ | ◯ | |
| 箕面教室 | ◯ | ◯ | |


